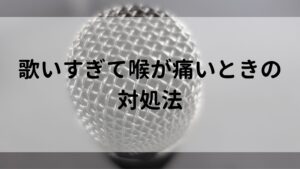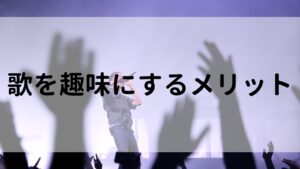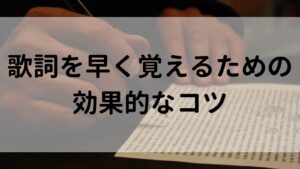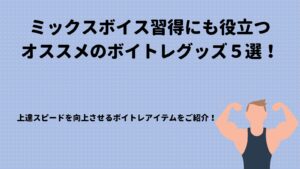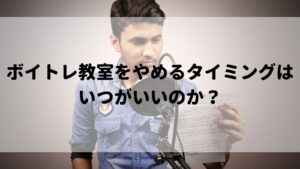あなたは通る声を出すことが出来ていますか?
「大声を出しているのにマイクに歌声が入らない」
「会話をしていて聞き返されることが多い」
「居酒屋で店員さんを呼んでも声が届かない」
「声がこもってしまう」
実は声が通らないことに悩んでいる人は多いです。
私も声が通らずに日常会話では聞き返されたり、一生懸命に歌を歌ってもお客さんの耳に届いていなかったりして、非常に悩んでいた時期があったのでこの辛さは分かります。
歌声がお客さんに届いていなかったら、それはもう歌っていないと同じことですからね。
ということで、自分自身では大きな声を出してるつもりでも、他人には届いていない経験があるという方向けに、通る声についての解説と出し方をまとめてみました。
通る声とは

通る声にの定義について説明不要かなと思いますが、念のため説明します。
周囲の環境音や雑踏の中の様に騒々しい場所でも声だけがすんなりと耳に入ってくる声が通る声です。
この通る声を出せている人って、声の大きさ・声量はそこまででもないのに、確りと聞き取れますよね。
周りの声・音から浮いている様なイメージですよね。
声が通らない人の特徴

姿勢が悪い(猫背や背筋が伸びていない)
声が通らない人に多く当てはまる特徴の1つに、姿勢が悪いことが挙げられます。
猫背で背中が丸まって、首が前のめりになっていたり、座った時に腰(骨盤)が立たずに座っていたり等ですね。
姿勢が悪いと見た目も健康にも良くないですが、何より発声に悪影響を与えてしまいます。
背中が丸まっていると、横隔膜を最大限に使うことが出来ずに中途半端な腹式呼吸、又は胸式呼吸となり、呼吸のコントロールをすることが出来なくなってしまいます。
呼吸のコントロールが出来ないがために通らない声しか出せなくなってしまうのです。
声を出すときだけでなく、日常生活において正しい姿勢で過ごして、癖付けをするといいです。
息の量と速さが足りない
上記で説明をした呼吸のコントロールに関係してきますが、通る声を出すには息の速さも必要になってきますので、呼吸のコントロールというのは非常に大事になってきます。
通らない声を出している人は発声時の息の量と速さが極端に足りていないのです。
口から息がぼわんと真下にこぼれ落ちるようなイメージですね。
こんな息に声を載せたとしても、声が前に飛んでいきません。声もぼわんと真下にこぼれ落ちます。
つまり通らない声となってしまうのです。
内向的な性格
声が通らない人って人と会話をするのが苦手な人や内向的な性格の人が多いと感じます。
この人たちに共通することは、自分を出すのが恥ずかしいという思いを持っているということです。
自分の存在を認知されたくないから、声も自然と小さい声、通らない声を無意識に出してしまっているのです。
実際、私も内向的な人間なので、無意識に通らない声や聴こえない声を出していました。
通る声の出し方

通る声の出し方についてですが、上記の声が通らない人の特徴の逆のことをすればいいわけですね。
また、発声技術の観点からも通る声の出し方を紹介したいと思います。
正しい姿勢で正しい呼吸をする
やっぱり姿勢って大事なんですよ。
この姿勢と言う土台が出来てないのに、発声したらやはり変な声になってしまうものなんです。
息の量と速さを上げる(腹式呼吸を意識する)
声が通らない人の特徴でもお話ししましたが、声が通らないのは吐き出す息の量と速さが弱いからです。
では、息の量と速さを強くするにはどうすればいいのでしょうか。
それは腹式呼吸を意識して、声を出すときにお腹の力で息を出すことです。
そうすることによって、息の量と速さを出すことが出来ます。
練習方法についてですが、背筋を伸ばし、腹式呼吸で息を吸います。
息を吸ったら、下に下がっている横隔膜を思いっきり上に引き上げて、息を「フー!」と強く出してみましょう。
これを何回か繰り返して、強い息の出し方の感覚を体になじませます。
その後、その感覚のまま「アー!」声を出してみて下さい。
息の量と速さが乗った強い声、通る声が出るはずです。
鼻腔共鳴を意識する
鼻腔共鳴、簡単に言うと声を鼻にかける、響かせることです。
身近な例を上げると、電車の車掌さんは鼻腔共鳴でアナウンスをしています。
あの独特の鼻にかかった様な声です。
変な声だなと思われるでしょうが、あの声って意外と通る声なんです。
注意深く聞いているとわかるのですが、電車のうるさい走行音に負けずにアナウンスがしっかりと聞こえるのは、この鼻腔共鳴をしているからなのです。
鼻腔共鳴のやり方について簡単に説明をします。
鼻に声をかける声になるのですが、最初は力が思いっきり入ってでもいいので、鼻に声を通してみて下さい。
口を閉じて、ハミングで「ン゛ー!」と鼻目掛けてやってみましょう。
声を出した時に鼻がビリビリと響いている感じがあれば鼻腔共鳴が出来ています。
このビリビリとした響きを掴んだら、その響きを残したまま、徐々に力を抜いていけば完成です。
この鼻腔共鳴をすることで、声が通る様になりますが、あまりにやりすぎてしまうと変な声になってしまうので注意です。
通る声のまとめ
通る声って良い発声をした結果、通る声になっています。
ですので通る声って客観的にみて良い声の人が多いです。
確かに音域や声量も大事ですが、マイクにすっと乗る通る声も出せる様に練習をしていくべきです。