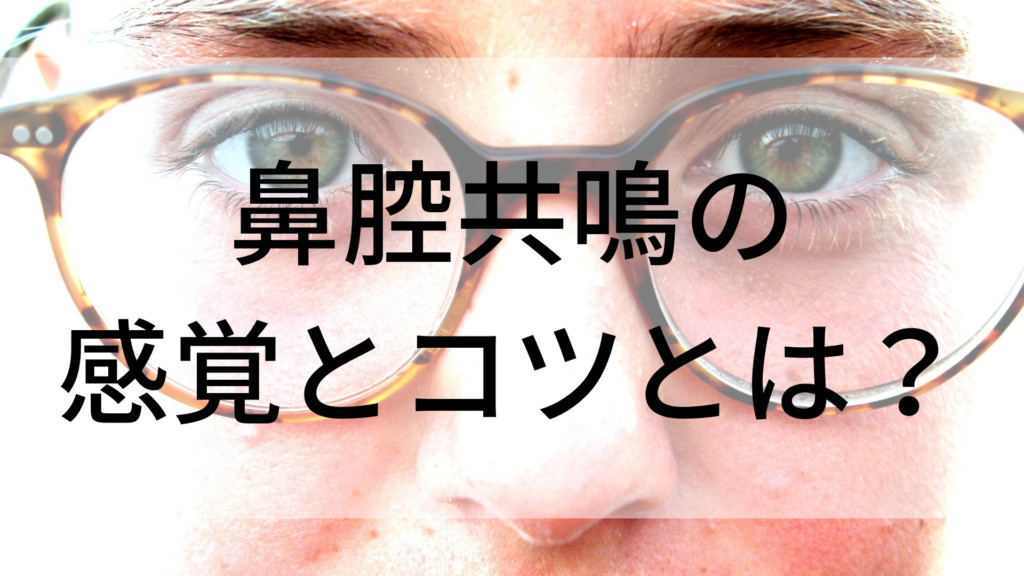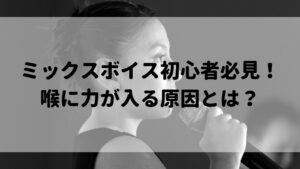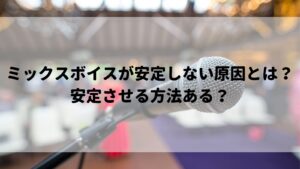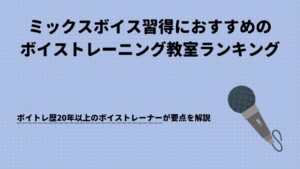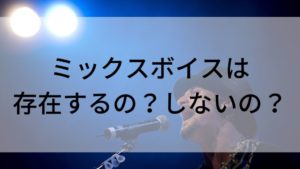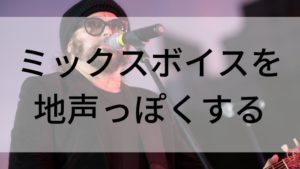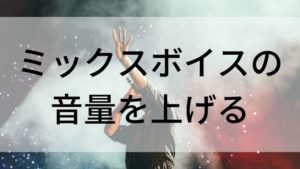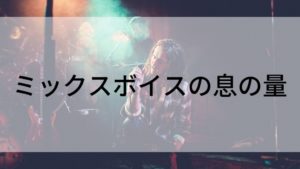鼻腔共鳴は発声の基本的な技術の1つです。
実はミックスボイスや高音発声をするために鼻腔共鳴というのは非常に重要な要素なんです。
鼻腔共鳴が何なのか分からない、鼻腔共鳴のためにどんな練習をすればいいのかについて、ボイトレ暦10年以上のボイストレーナーが鼻腔共鳴について解説をしていきます。
ここで鼻腔共鳴についての疑問を解消して、発声のレベルアップを目指しましょう。
鼻腔共鳴とは
その名のとおり、声を鼻腔に共鳴させることです。
少しだけ鼻にかかっている様な声、いわゆる鼻声っぽい声です。
ちなみに鼻声とも違うものです。似て非なるものです。
この少しだけ鼻にかかっている様な声というのが鼻腔共鳴のポイントなります。
それでは1つずつ解説をしてきますね。
鼻腔共鳴はプロ歌手も使用している
もちろん、プロの歌手も鼻腔共鳴を使って発声しています。
分かりやすい例を挙げると、ガルネリウスの小野正利さんやエックスジャパンのtoshiさん、ミスチルの桜井さんですかね。
人によっては「え?その人達の声って鼻にかかってるようには聴こえないんだけど?」と思うかもしれません。
これも自分が鼻腔共鳴を出来るようになると聴き分けられるようになります。
「あ、この人は鼻腔共鳴を強めに出してる人だな」とか「この人は鼻腔は全然使ってないけど、所々で鼻腔共鳴を使った発声をしてるな」とかですね。
鼻腔共鳴の聴き分けが出来るようになるレベルになると、鼻腔共鳴が出来ていると言っても間違いではないと思います。
鼻腔の場所ってどの辺り?

人によって感覚は違ってきてしまいますが、鼻腔は基本的には鼻の奥、口の中の空間の上にあります。
顔の中心部に空間があるようなイメージでしょうか。
直接的に鼻腔を感じ取るには、ワサビや強めのミント味のタブレットを食べた時に鼻がスースーしたり、ツーンとしたりしますよね。その辺りが鼻腔に近い場所となります。
その辺りに鼻腔があると意識をして、続いて次の記事も読み進んでいってください。
鼻腔共鳴のメリット

鼻腔共鳴が出来るようになると、声に鼻の響きを乗せることが出来ます。
鼻の響きが入ると発声にとって様々なメリットがあるのです。
響きの乗った良い発声が出来る
鼻腔を共鳴させると、歌声に響きの要素が追加されます。
例えばマイクのエコーをイメージしてください。
エコーを切った状態とエコーを入れた状態では、エコーの入った状態の方が歌が上手く聴こえますよね。
鼻腔共鳴は自分の鼻を使って、そのマイクエコーを自分の好みで入れることができます。
マイクエコー無しでも鼻腔共鳴をすることで充分に魅力的な発声が可能となります。
また、声に響きをつけるには、その出している音域にあった場所に声を当てなくてはいけません。
基本的には、低音なら胸や喉付近となりますが、中音や高音なら声を当てる場所は鼻や頭、うなじになります。
鼻腔共鳴は正に、中音や高音で響きをつける場所の1つである鼻への共鳴を得られることが出来ます。
この共鳴の響きがないと、声が薄っぺらくなってしまい、素人感のある発声となります。
声量が上がる
声量が上がるというよりも、リスナーに対して声量があるように思わせられる発声が出来る様になります。
息の力を強くしなくとも、鼻腔へ響かせることで、少ない発声エネルギーでも充分な声量を出せるようになります。
鼻腔は例えるなら大きなドーム上の空間になっています。
広い体育館とかホールで声を出すととても響きますよね?
それと同じく鼻腔で響かせることによって声量も上がるのです。
高音域も楽に出せるようになる
高音域に近づくにつれて、鼻腔共鳴を意識していかないと無理な発声になってしまいます。
というのも、出している音域にあわせて、響かせる場所も意識して動かす必要があります。
低音域は胸、中音域は口、高音域は鼻、又は頭にといった具合ですね。
もしも高音域を出しているときに、鼻ではなく胸や口の辺りでしか響きを持つことが出来ない場合は鼻腔共鳴を意識して、鼻に響きを集めると高音もすんなり出せるようになります。
自分でやってみるとお分かりになると思いますが、高音域を胸に響かせるのはとても難しいですし、逆パターンで低音域を鼻に響かせるのも難しいはずです。
高音域では鼻、つまり鼻腔共鳴を意識するのが高音を出す要素の1つです。
地声と裏声の切り替え(換声点)がスムーズになる
換声点付近って非常に不安定になりがちな音域ですが、鼻腔共鳴を意識することでブレイクせずにスムーズな移行が出来るようになります。
地声と裏声の切り替えが上手くいかないのは、響きの位置を切り替えていないことが理由の1つとしてあります。
上述したとおり、出す音域に合わせて響きの位置も変える必要がありますよね。
それは換声点にも言えることなのです。
胸に響きを乗せたままで裏声へ移行しようとすると、高確率でブレイク、つまり裏返ってしまいます。
ですので、裏声に切り替える前、なるべく早いタイミングで鼻腔共鳴を意識してみると上手く裏声へ移行できます。
鼻腔共鳴のコツ
鼻声を意識する
前述しましたが鼻声と鼻腔共鳴は似て非なるものです。
どちらも鼻に声が入っている状態ですが、入れ方の強さが違います。
僕個人の感覚になりますが、鼻声は鼻に90%以上の声を入れている状態ですが、鼻腔共鳴は30~70%程度の割合で鼻に声を入れている感覚です。
最初の内は鼻に声を入れる割合の細かい調整が出来ないor難しいと思います。
そのため、まずは鼻に100%声を入れるところからスタートするのがおすすめです。
鼻100%の状態で喋って見たり、発声練習をしてみて、鼻腔共鳴の感覚を探っていきます。
慣れてきたら、鼻100%から90%、90%から80%と割合を下げていきましう。
鼻10%まで下げることが出来たら、鼻腔共鳴を調整する感覚が身についているはずです。
そのレベルまできたら音の高さと鼻腔共鳴の割合を試行錯誤していきます。
「この音の高さは鼻50%入れないとすんなり出せないな」
「hiCは鼻70%で安定しそう」
「hiGは鼻90%いや120%じゃないとダメだ」
とか考えつつやってみると上達スピードもその分速くなります。
鼻腔共鳴の練習方法
練習方法についてはこちらの記事でまとめています。
鼻腔共鳴のまとめ
鼻腔共鳴が出来ているのと出来ていないのでは歌声に雲泥の差が出ます。
鼻腔共鳴が出来ると声の響きも増して、声量や音域も広がって、聴く人に感動を届けられる歌声になります。
鼻腔共鳴の感覚が身につくまでは、歌を歌うときは常に鼻腔共鳴を意識するようにしてみてください。
しばらくすると、無意識の内に鼻腔共鳴での発声となり、プロの歌手の様な歌声に少しずつ近づいていきます。